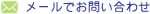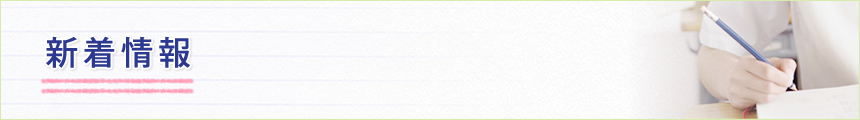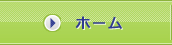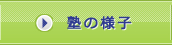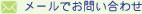- ホーム
- >
- 新着情報
時を心に刻む
- 2022年10月24日
- 私は教科書や講習会テキスト、国語の題材から学ぶことが結構あります。
気になった文献はアマゾンで実際に買って読んだりします。
というのも、扱っている文は長文の中の一部だからです。
講習会テキストで、「ファンタジーの発想/小原 信」を扱ったものがありました。
分類としては随筆文ということになります。
読み始めたものの、なかなかその部分に至りません。
ひょっとして、タイトルを誤ったか?とも思いましたが、その部分に至りました。
簡単に抜粋したいと思います。
-------------------------------------
われわれは何年生きても、どんなに忙しくしていても、もし心に感じなかったら、
その時間は「無い」のと同じことになる。心に感じる時間とは、その間に何かがあって、
自分が生きていることを実感することのできる時間である。そういう生きた時間はあまり忙しすぎるとなくなってしまう。
少しの無駄も遊びもなくなると、落ち着いてしみじみと何かを考えたり感じたりすることができなくなってしまうのである。
三十分より長い五分があり、三分より短い三時間がある。それがわれわれの人生なのだ。
出会いとして心に残る出来事は、時間にしてほんの数秒の出来事であるのに、
それがどうかすると一生を左右することにもなりかねない。その場合は、わずか数秒が何十年よりも長いということになる。
その一瞬は瞬間的なことであるが、その一瞬を何度も反芻しながら何十年も暮らしていくような、そういう人生はあるのである。
時間とは自分が意識してかかわる対象である。主体的にとらえられた時間は、幼年時代というものがそうであるように、
ただそこに見つめ眺める対象としてあるのではない。自分の方から積極的に関わっていく関わりとしてある。
同じ学校にいた人と聞かされても、学生のころ話したことがない人は、自分にとってはいなかったのと同じかもしれない。
今我々の周りはそういうどうでもいい人間や時間に満ち溢れている。つまり、すべてがむなしいのだ。
自分が知らなかったこと、気づかなかったことの数々は、自分にとっては無かったのと同じである。
異なった言葉や文化について無知な人と、その国の歴史や地理について何もわかっていない人は、
知っていればとてもそんなことは言えないことを平気でいうことがある。知人のいない国は懐かしくもなんともない。
友人の来ないパーティはつまらない。自分がそれに対し進んで関わろうとするものは決して単に見つめるだけの対象となることはない。-----中略
やさしさの問題は、ものをあげることではなく、時間をあげることにおきかえられる。
相手の話をだまって聞いてあげるというのは、やさしさを定義しなおしたものであろう。
考えてみると、時間というのは、その人のそのときのすべてである。
ものをあげるものは持っているものの一部をあげることであるが、時間をあげるというのはその人のそのときの全部をあげることなのだ。
病人をなぐさめお見舞いをするというのも、見舞いの品物だけを郵送するとか持ってきてすぐ帰る人もいるだろうが、
できればしばらく病室にいて話をしてくれる人を病人は喜ぶことがある。
もうそれほど食べることができなくなった人に対しては、何かを持っていくより、
しばらくじっとそばにいてあげるだけで、そのこと自体が一つの贈り物になっているのである。
しかし、多くの人はスケジュール表や手帳に空白が目立つことがさびしいから、
なるべく空きが無いようにしておいて、約束の多いこと、忙しいことを得意になっていることがある。
そういう人は、忙しさを楽しんでいるうちに、忙しさのあまり何が大切なことかがわからなくなってしまう。----略
-------------------------------------
家族、友人に関わる自分に置き換えて身につまされた方はいませんか?
私はずいぶんと身につまされました(汗)
スマホやツイッター、Line、SNS、ブログ、ゲーム等に忙しくて、大事なものを見失っていませんか?子供におもちゃを与えるだけで、
一緒に関わろうとしていない方はいませんか?文明の発達と幸福度は必ずしも比例しないと思うようになりました。
むしろ反比例するようなところもあると思います。大昔の人も現代人も同じように一日24時間与えられてきたはずですが、
家族が一緒に過ごす時間は発展途上国の方がむしろ多いのではないでしょうか?
私はネパールを訪問しようと思っていましたが、彼らの素朴な生活に触れてみたいという思いがありました。
残念ながらコロナ禍によりその願いは叶っていません。その隣のブータンという国も幸福度の高い国です。
どちらの国も、GDPは190カ国の中で底辺の国です。昔ながらの生活がそこにあります。
国語というのはただ読んで文法や語彙を学び、読解をするのでなく、題材をじっくり味わい、
そこから何かを学び取ることが大事ではないかと思います。
そのためにも、一部を抜粋した教科書や講習会テキストを読むだけでなく、
実際に図書館で借りたり、アマゾンで注文したりして1冊まるごと読まれることをお勧めします。
というわけで、12月末から冬期講習会が始まります。ぜひともご参加ください♪